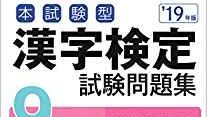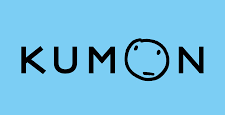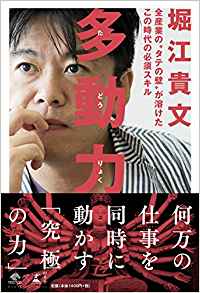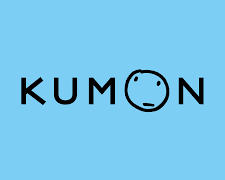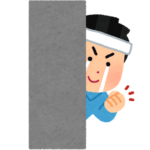各教室を訪問してレポートを載せている。無料見学会や体験学習に行く前に読んでから行こう。気になる点を絞って教室に行かないと、ただ行っただけになってしまいますよ。
Twitterメモ
子どもの自学する力を育むkumon
を読む。
続けて公文式の本が読みたくなったので読みます。https://t.co/lT0ZdfyOZF— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月28日
エコールマミ教室の南浦先生
この教室、進度一覧表に名前のあるとこだ!
インタビューを読む限り、やはり子どものちょうどを見つけ、やる気を出させるのがうまそう。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月28日
子どもの手が止まり、頭が上がってきた時が、行き詰まったとき。
そのタイミングを逃さず声をかける。
これが、無料体験で、わかるいい指導者かどうかを見分けるポイント。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月29日
ちょうどの意味は、精一杯頑張って解けるレベル。
楽に解ける意味ではないが、なんとか解けるレベルを意味する。
最初は簡単だけど、後になると難しくなっていく。それでも例題を見れば解ける。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月29日
それぞれレベルが違うが、似たようなところをしている子どもを見つけると、自分も同じようにしたいと思うようになる。
だから、できるようになる。
たしかに子どもは真似っこ。分かる気がします。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月29日
くもん教室は、私語はない。
だが、お互い助け合いの精神はある。
くもんの外に出ればたくさん話をするんだ。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月29日
いい先生の教室には、元教え子の子どもが入ってくる。
さらに噂が噂を呼び、遠方から通う人もいる。
この辺りを口コミで聞けると確かな評判になるだろう。
エコールマミ教室は、そんな教室です。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月29日
優秀な先生の元には、受験で中断しても最終教材まで終わらせにやってくる。
いい先生に巡り会えることは、幸せです。
子どもにとっても強い味方だし、親にとっても頼もしいのです。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
大学生になれば、採点のバイトに戻ってくる。
結婚式の日取りが決まれば、招待状を送ってくる。
ここまで、信頼関係ができると親も嬉しい。
長くできる習い事の一つだ。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
親以外の信頼の置ける大人を作る。
いつの日か親の言うことを聞かなくなる時期がくる。
その時頼りにしたいのが学校の先生とか。
だが、信頼できる担任に出会うか怪しい。
親がサポートしてあげよう。優秀な教室には、優秀な大人が多数いる。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
童謡をたくさん聞いて育っている子は、明らかに語彙が多い。
そうなのか?
我が子もたくさん歌を知ってると褒められたことがある。
確かにドキッとする言葉を言うときあるけど、同じ年の子と変わらない気がしてる。
まだまだ足りないのか?あまり肌感覚と一致しない。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
国語の力が上がってくると、キレなくなる。言葉の表現が増えて、感情を言葉にできるからだ。
心も育つ公文式。
我が家の娘らも順調に育ってる。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
算数ができるようになると、道筋がたてれるようになる。
問題解決までの見通しだ。
小さい頃から訓練してできるようになるには、算数を学ぶのがいい。国語を学べば、語彙が増えてキレなくなる。
少年院で公文式を教えた結果だ。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
子どもに努力する経験をあげる。
大人になっていけば、勝手に努力を始めることはない。
幼児教育を勧める理由はここにある。
習い事は、親の負担が大きいから、家庭でやるのが一番コスパがいい。だが、意志が高くないと続けるのは難しい。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月30日
語りかける言葉が少ないと出てくる言葉も遅い。
本当は、親が付いて子どもに歌や語りかけをたくさんしてあげるのがいい。
でも現実には、親が疲れる。
子どもが増えたり、共働きになったら余計に疲労する。
だからぼくは外力を頼る。公文式や幼児教育なら、強制力が働くからだ。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月31日
家庭学習の習慣が難しい。
簡単に娯楽が手に入る時代。ますます、机に向かいにくくなる。
家庭で守れるルールを作って守らせるのがいいのだが、ちょっと大きくなると難しい。
我が家は幼い頃にくもんを始めたので、家庭学習の習慣はついた。45分ぐらいは座ってできる。
次は次女のばん。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月31日
神奈川県津村教室。
公文式の神奈川県ランキングにも載る教室。言われるように国語に力を入れてる。
教室の壁に本を並べてすぐに本がある環境だ。
我が家も少しだけ本棚がある。
結構、本を読むと思う。
おしりたんていだけど。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月31日
子どもはリズムのあるわらべ歌が好き。
傾向だろうが、我が家もそう。
ちびすけどっこい、とか好き。
こういう好みが分かるなら、好きなものから始めるといい。
教材にあるものを選ぼう。読んだことあれば、興味も湧くはず。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年5月31日
子どもも新しいこと、難しいことをするとき、怖くなることもある。
公文式もスモールステップの進度だが、子どもが難しいと感じて逃げ出したいと思うことがある。
自信を取り戻してあげることが大事。ある程度続けると子どもに任せてしまうが、注意が必要です。https://t.co/8qPVBoOh0J— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月1日
決断は子どもに任せる。上から指示するよりも持続する。
たしかに自らの決断は、責任も伴う。子どもの頃から経験させるのは、いいことだと思う。ただ、手助けはしてあげないと任せっぱなしは無理がある。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月2日
プリントの宿題をする我が子が当たり前だと思わない。
最近は、毎日泣かずに宿題するので、当たり前になってたけど、スモールステップとはいえ、子どもにとっては大変なこと。
毎日の宿題は褒めてあげる。大切なことです。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月2日
近くにくもん教室があるのに、車で30分の教室に行く。
そうなんだよねー。やはり我が子や親に合った先生が一番。
熱意のある先生だと頼りにしたくなる。くもんは親の努力必須だけど、先生を信じれなくなると続けられない。
親の負担大だから、分かってもらえないと親が先に不信感持つ。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月3日
プリントは悪くないし、当然子どもも悪くない。
どこまで先生を信じて付いていけるかだと思う。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月3日
くもんではライバルは、自分自身。隣の人は気にしない。
過去の自分と向き合うこと。宿題ができることは、過去の自分に打ち勝つこと。
できないことはない。そんなプリント。
ここがミソ。
先生が未熟なのか、子どもにあってないのか、努力がたりないのか、見極めないといけない。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月3日
公文式は、究極の個人別指導。
子どもの個性を重視したプリントの進め方です。
となれば、その見極めをする先生が重要なんだ。
どこでも同じ指導が期待できるわけじゃない。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月4日
子どもは、勉強や宿題が嫌だというが、終わってみると笑顔を見せる。
いい笑顔するんだよね。
我が家の5歳長女もいつしか宿題が嫌だと言わなくなった。
勉強習慣が完全に身についたし、声かけだけで進んでこなす。
気持ちの変化は聞いてないけど、やりたいって思うはず。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月4日
我が家の5歳長女は、遊びたいと思ってる。
もちろん遊ばせる。
だけど、同時に学びたいって意識も忘れてない。
幼稚園では、ひらがなを使った言葉遊びをしてるけど、誰もが知らない言葉を探すと張り切ってる。
負けなくないって気持ちはあるから、いい傾向だと思う。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月4日
公文式で大学受験突破
著書の中では多いらしいけど、実際は少ないはず。
20年前にくもん生なんて周囲にいなかった。
田舎だからかもしれないが、公文式なら、続けていれば、3学年進むはず。
だから中3では、高校課程も終わるだろう。高校から塾が多いはず。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月4日
勉強はなんのためにがんばるか?
自分のためだと言うのは、ナンセンス。
人の為にがんばるからこそ、素晴らしいものが、達成できる。
世の中のためになることを成し遂げるために勉強する。
これが理由。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月4日
学年を超えて勉強すると、勉強が楽になる。
小学生の感想らしいけど、その通りだ。
ぼくも半月くらい入院していた時期があった。親父が算数を教えてくれたが、結構先取りした。
それから授業を受けても理解してるから余裕を持って理解できる。
勉強が楽しいと記憶あるのは、その頃から。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
それが無かったら、勉強が楽しいなんて、一度も思わなかったかもしれない。
先取りは、有りだと思う。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
小学生の英検合格者の3人に1人がくもん生。
そんなデータあるんだ。
しかも、小学生から英語の授業が始まる。
先取りしとこう。イーペンシルは、素晴らしいです。
外国人には、大人になってからでも慣れる。お金があれば、英語で授業してくれる小学校にいれれば、いい。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
でも普通のサラリーマンには、無理じゃない?
子ども3人、私立に入れる余裕はないです。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
公文式は、高校数学の微積分を解くための最短ルートを取る。
時計、図形、文章題は、ほぼない。
中学受験が視野にあるなら、算数は、早々とやめていいと思う。なぜなら、勉強のベクトルが違う。無駄な努力なのでやめていい。
だが、国語と英語はちょっと違う。中学受験の国語は、まぢ難しい。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
なぜならその夏流行った書籍から出題される。
大人向けの本なんだ。これを小学生が解く。
ぼくは当時内容を読めていただろうか?
くもんの教材は、縮約がある。内容を理解しないとできないことだ。教材には、大人向けの本も出てくる。最終教材を終わらせる価値あると思う。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
英語もそう。
まだ中学受験に英語は早いが、娘が中学受験の頃には、英語も必須だろう。
つまり、問題のレベルは不明だが、とりあえず続ける価値はある。— おかぽん@5y🚺2y🚺7m🚺定時帰宅中 (@okapon1979) 2019年6月6日
勉強の意味を明確に表現してくれてる。自分のためではなく、人のため。賢くなれば、助けられる人の数が多くなる。これだね。
公文式は、個人に合わせて進んでいくのがメリット。集団教育ではないので、ヤキモキすることもない。ただし当然だが、デメリットの記載はない。そこも知っておいたり、考えたりする必要はあるね。